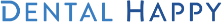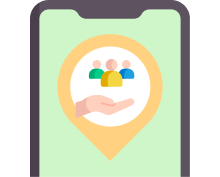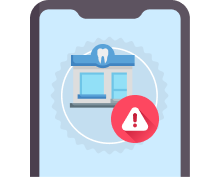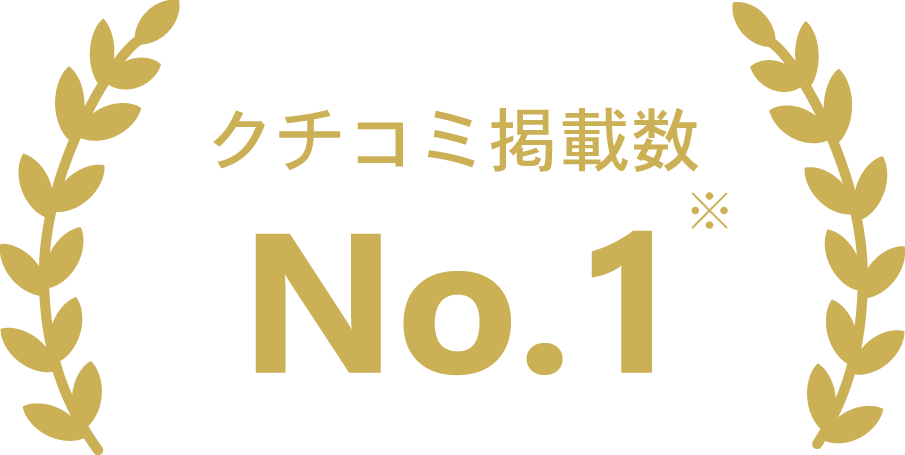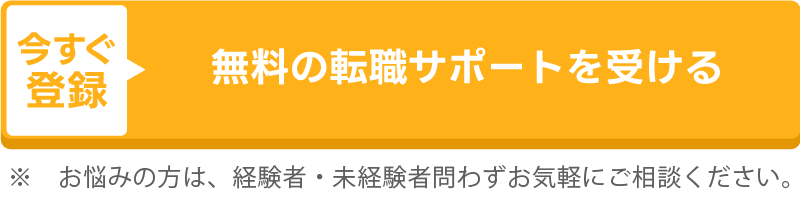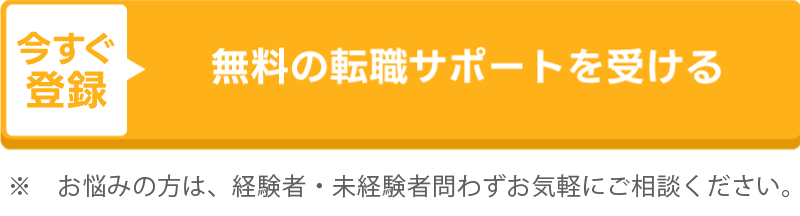歯科業界を問わず、スタッフが個人の能力を最大限に発揮する前提条件として【心理的安全性が保たれた環境】が重要だと近年言われておりますが、皆さんは【心理的安全性】という言葉をお聞きになられたことはありますでしょうか?
心理的安全性とは、簡単に言うと『ありのままの自分でいることができる環境』。
今回はまず理解を深めるために、心理的安全性の低い職場とはどのようなものかを解説して行きたいと思います。
心理的安全性の低さはスタッフの定着率の低さも繋がりますので、ご注意を!
心理的安全性とは、簡単に言うと『ありのままの自分でいることができる環境』。
今回はまず理解を深めるために、心理的安全性の低い職場とはどのようなものかを解説して行きたいと思います。
心理的安全性の低さはスタッフの定着率の低さも繋がりますので、ご注意を!
心理的安全性とは
.jpg)
心理的安全性と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
「安心して働ける職場」
「ストレスがない職場」
「アットホームな職場」
字面だけ見るとこんなイメージにとられることが多いのではないでしょうか。
実際は「個々人が恐れや不安を感じることなく発言・行動ができる状態」を指します。
元々はハーバード大学で組織行動学を研究していたエイミー氏が提唱したものですが、昨今では日本の組織でも取り入れられることが増えてきました。
「恐れや不安を感じることなく発言・行動ができる状態」
というのは噛み砕いていえば
「この組織であれば無能と思われる発言やネガティブと思われる発言をしても大丈夫だ」
という信頼関係がある状態でもあります。
そして歯科医院の中には心理的安全性が低いがために、スタッフが早期退職してしまったり、長く働くスタッフがいるものの、どこかギスギスしている職場があるのも事実です。
「安心して働ける職場」
「ストレスがない職場」
「アットホームな職場」
字面だけ見るとこんなイメージにとられることが多いのではないでしょうか。
実際は「個々人が恐れや不安を感じることなく発言・行動ができる状態」を指します。
元々はハーバード大学で組織行動学を研究していたエイミー氏が提唱したものですが、昨今では日本の組織でも取り入れられることが増えてきました。
「恐れや不安を感じることなく発言・行動ができる状態」
というのは噛み砕いていえば
「この組織であれば無能と思われる発言やネガティブと思われる発言をしても大丈夫だ」
という信頼関係がある状態でもあります。
そして歯科医院の中には心理的安全性が低いがために、スタッフが早期退職してしまったり、長く働くスタッフがいるものの、どこかギスギスしている職場があるのも事実です。
心理的安全性が低い職場とは
.jpg)
- 無知だと思われる不安(こんなことも知らないのか…!)
- 無能だと思われる不安(この人仕事できないな…!)
- 邪魔をしていると思われる不安(あの人が発言すると打ち合わせが長引くな…!)
特定の人に発言が偏りがちになってしまい、新たなアイディアや意見が出にくくなってしまいます。
- ネガティブだと思われる不安(この人の意見は批判的だな…!)
これらの不安要素が強い職場では、自分自身の自己開示性が低くなることで、適切なコミュニケーションが取れなくなり効率的な働き方が難しくなってしまいます。安心して発言ができない職場というのは想像以上に心を病んでしまうもの。それだったら退職をしてしまおう…と考えてしまうのです。
自分のクリニックは団結力があり問題ない!と思っている場合でも、逆にその団結力が「ありのままでいること」に歯止めをかけてしまう、という落とし穴もあるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は心理的安全性について、まずはその概要と、心理的安全性が低い職場で起こりがちな問題について解説させていただきました。
次回はいよいよ心理的安全性を高めることで期待できる「ありのままの自分でいられる」組織作りについて、具体的に解説していきます。
定着率に直結するからこそ大事なポイント、お見逃しなく。